子供が皆、高学年以上になった我が家。
小さかった頃は、ママ友と子供の勉強や子育てのことを詳細に話していた。
成長するにつれ、個人差もあり共通の話題だった勉強の詳細は話さなくなった。
子供が高学年になってよく聞くママのセリフ。「もう勉強はあきらめた。特に算数」
小学校高学年 算数 あきらめていい??
小学校算数 あきらめるタイミングは高学年?
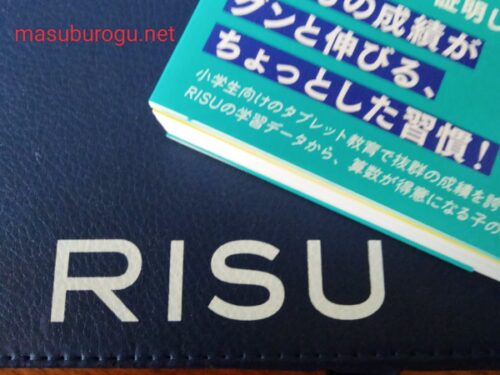
最近、何人かのママから同じことを聞いた
✅宿題やってないみたい。
✅ドリルの答え見て書いてるみたい。
親との接し方も変化した。まだ手がかかるところと、しっかりしてきたところ。
こちらの行動もよく見ている。時に親の目が向いていないことも、気がつかれないことも知っている。
どうにかバレずに、すり抜ける方法もある。
子供なりにどうやって攻略しようかと考えた末の方法。
結局、バレて怒られてた。
子供は、やり直させられる時にも「やっぱりめんどくさい」
怒られたからやるけど嫌いは減らない。
親は親で早めの判断をしてしまう。
「もう勉強好きじゃなさそう」
「言うこと聞かない」
「やっても無駄だと思う」
「そのうち塾にお任せする」
自分がいいと思うなら、もうそれでいいかなと思って(←これめっちゃよく聞く)
そんな理由から子供の勉強をすでに「諦めた」と話す高学年のお母さんは少なくない。
小学生のうちはのびのびやらせて、中学で塾に入ってなんとかしてもらう(←これもよく聞く)
「すでにママもめんどくさくなってる」
高学年になったから…と親も一息ついちゃうところはある。気持ち分かる。
でもね、取り返せないんす…「後から後悔しまっせ」
言えない理由は個人差「拡大する高学年」
✅育て方の違いで生まれる差
同じように育てている兄弟ですらある「個人差」とその家「独特のルール」
✅置かれた状況で生まれる差
中学受験・習い事に全振り・まだ何も決めてないから自由。
子供をどんな風に育てるか?で子供の状況とその後の方向も変わってきた。
経験から…
立ち話の中ではこんなことは言えない。だけど、本当はこう思っている。
「あきらめるのは今じゃない」どう育つか?どんな影響を受けるか?
高学年で子供はまだ「何も決まってない」
あきらめてしまったら、もったいないのですよぅぅぅ。
算数 あきらめてはいけない高学年
広がる個人差の理由
私達の小学校時代は、皆が一斉に正しい事と正しくない事の認識を同じくしていた。
横にいる人と同じことができなければ慌てて頑張った事も珍しくない。
小学校では皆一列で同じことを頑張った。
できてもできなくても、一応やらされた。
今は「多様性」とか「個人の尊重」または「能力差はあるもの」として一律でなくてもいいという考えに。
主張すれば通りやすい(笑)
個人の価値観の上に成り立つ選択の範囲が広くなり、受け入れられる。
小学校でも自由が幅をきかせている。
宿題をやらない、カンニングした宿題でも先生は怒らないみたい。
…怒ってくれていいんですのに。
その家のルールが通りやすいから、子供は昔より様々。
先生や周りの大人が怒ってくれない。昔より、家庭の育て方で決まる。
いいか悪いか別として、親の育て方がそのまま出る。……責任重大過ぎる。
で、子供が宿題をカンニングする理由。
「もう勉強が楽しくない」からで、楽しくないのは「分からないから」
分かんないところが結構あるのに、友達はできてるみたい。しかし自分はできない。
けど忙しそうな親には聞けない。
「何が分からないか、自分でも分からない」だから、先生にも聞けない。
テストでもやっぱり分からない。嫌い。
半ばあきらめて、宿題だけをとりあえず終わらせている。という感じかな…と思う。
これは私が高学年の時に自分が体験したことでもある。すでに算数は苦手だった。
実際に、夏休みのドリルは答えを写してた
ちなみに私はバレなかった。昔は今よりみんな細かくなかったかもしれない。
だから、のちに算数はあきらめた。
算数は答えが一つしかない。
早とちりすると、小学校算数はコツさえつかめば。公式さえ覚えれば。計算問題さえ完璧ならば。と「その答えが正解か?」ということにこだわってしまう。
もう嫌いで訳が分からないから答えも出ないし「あきらめる・算数やめる」になる。
あきらめないとどうなる?
小学校算数をあきらめた母が育てる
「算数の得意な子供」
RISU算数を軸に家庭学習をしている我が家。小学校で一番家で勉強した教科は「算数」
やり続けたメリット=算数に真正面から向かった時間の長さ・小学校の算数に浸る
毎日のようにRISUにログインして、1問でも算数の問題に触れる。
色んな種類の問題を毎日すこしずつ解く。
低学年の時には難しいと聞いてきたり、時には泣くこともあった。
今は時間がかかっても、自分で解く。
小学校の時に色んな種類の問題を解く・自分なりに自分のペースで算数に向かっていく。
勉強をしているというよりクイズに挑戦しているような雰囲気。
毎日のルーティーンに組み込まれると「やらされる勉強」は存在しなくなる。
「あ、ちょっとこれ分かんない。」
…困ったな。もう私教えられない。
「お兄ちゃんが帰ってきたら見てもらう?」
さっきの問題どうした?
「あ、あれ分かったよ。よく読んでみたら2行目にヒントがちゃんとあった」
これが最近の子供との会話。
算数は単純に答えを出す教科でなく「ああかな?」「こうかな?」と考えて試行錯誤し答えにたどり着く。
答えを出した後も、これでよかったかな?
もっと簡単に出せる考え方はあったかな?
答えを導きだすプロセスを楽しむことが算数の醍醐味だ。RISU算数を日常的にやるようになって、子も親も算数に対する認識がずいぶん変わった。ドリルの答えを写していた私が良く言うもんだ(笑)
小学校算数にじっくり取り組む時間が習慣化した結果
「学校の算数の成績がいい」とか「テストの点数がいつも良い」に加えて”豊かに成長している”と説明できる。
最近よく言われる「論理的思考」が備わってきたなと感じる。
じっくり考えれば分かってくるという自信。
物事を始める前に全体の把握をして、認識してから事にあたるという計画性。
落ち着いてますね…って思う(笑)
算数を基本に頑張って来たからだなと感じることが多い。
しつこく何度も言う。中学生とか高校生って本当に忙しい。なんとかするの大変。
あともう一つ。「塾は魔法学校じゃない」伸びるも伸びないも子供次第。
これって受験を経験して分かった(→めちゃ持論)しかしホント。小さく書く。
まだまだ続くよ子育てと勉強
早道よりも寄り道や戻り道
「コツはなに?今から劇的に成績を上げる方法は??」
「やっぱ課金しかないよねー」
と算数の計算問題だけあってればいい!!みたいな (←けっこういる)ママからすると
とてつもなくアナログかもしれない。
しかし、この小学校時代の「あきらめない算数」ゆくゆく子供の強さになると信じられる。
高学年も遅くない!
子供が小学生のうちにやり直す・あきらめない。今はまだ時間がある。
できるところまで戻って少しでも分かるを増やす。分かれば面白くなる。
つまづいたところが分かれば「そこから戻ってやり直す」今はまだ時間がある。
なんとなんと長い夏休みもすぐそこ(笑)→暑すぎる夏休みだから、家に居る時間だけはある。怖いですね。
長男が高校生になった今、この「小学生時代の時間」はいかに貴重で有効かが分かる。
大きくなったなー、手が離れてきたなーと思っても、写真を見るといつでも今よりはるかに小さく、そのかわいらしさにびっくりすることがある。その時必死で気が付かなかったな。大切な時間だったな。と振り返る。
ちゃんと育てていけてるのだろうか?と不安ながら、しかしその都度いつも一息ついちゃって…。
もう大きくなったから…と思ってしまっているのだけど。
「あの時ああしておけば…」とならないよう小学校時代をあきらめず大切にしたい。
まだまだ終わらないね。頑張りたいね。
本当は自分のママ友にもこう話したかった。
だけど、自分の持論ばかりを押し付けられない。そんなもやもやを書いた「小学校算数のあきらめ注意報」
参考になると嬉しいです。
我が家の目標
1小学生のうちは家で勉強を見たい。
2小学校の算数は小学生のうちに完璧にしたい
子供の家庭学習の習慣を継続すると色々な変化があった。
RISU算数を家庭学習の軸に毎日続けた経過や思うことをずっと書き続けています。
我が家はこれで家庭学習が習慣になった。
どのページを読んでくれてもどのリンクからも同じキャンペーンページへ行きます。
RISUきっず https://www.risu-japan.com/lp/kids/yan07a
RISU算数https://www.risu-japan.com/lp/yan07a
夏休み試してみるのもアリかも
お得なキャンペーンを受ける方法はこちら




